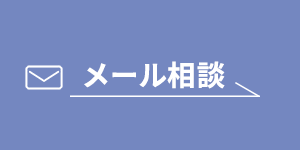建築基準法における内装制限のルールとは?違反するリスクや対策方法も解説
著者:八幡建装 株式会社
「建築基準法に内装制限ってあるけど、うちのテナントも対象なの?」
「どんな内装材を使えば法令違反にならないんだろう?」
そう思う方もいるのではないでしょうか。
建築基準法における内装制限は、建物の用途や規模によって異なり、誤った判断は法令違反や検査不合格、開業遅延といったリスクに直結します。
だからこそ、自分の物件が内装制限の対象かを正しく把握し、適切な対応を取ることが重要です。
本記事では、建築基準法における内装制限の定義や対象となる内装部位、使用できる内装材の基準などを詳しく解説します。
八幡建装は、千葉県市川市や船橋市、東京都23区を中心に店舗内装工事を行っており、特に美容室の施工実績が豊富です。
無料で物件選びに同行してもらえるため、お客様の理想に近い物件を選びやすく、完全自社施工管理により中間マージンも一切ありません。ぜひ一度相談してみてください。
目次
建築基準法における内装制限とは?
店舗や事務所などを新たに開業する際、見落としがちなのが「建築基準法における内装制限」です。
これは建物内部の仕上げ材に関するルールであり、特に火災時の安全性を確保するために設けられています。
ここからは、建築基準法における内装制限のルールについて深掘りしていきます。
内装制限の定義と目的
建築基準法における「内装制限」とは、火災時の延焼を抑える目的で、建物内部に使用する内装材に耐火性能を求める規制のことです。
特に不特定多数の人が利用する施設では、避難の妨げを最小限にすることが重視されており、一定の部位には「不燃材」や「準不燃材」などの使用が義務づけられています。
国土交通省が定める建築基準法施行令第128条の3などに基づき、燃焼性試験をクリアした認定材料であることが必要です。
このような制限は、火災による煙の発生や有毒ガスの拡散を抑制するという観点でも、重要な役割を担っています。
どんな建物・部位が対象になるのか?
内装制限の対象となる建物は、劇場・映画館・百貨店・飲食店・学校・病院など、不特定多数の人が利用する用途に該当するものです。
| 居室 | 通路・階段 | |
| 特殊建築物 └自動車車庫、自動車修理工場、撮影スタジオ | 壁・天井:準不燃以上 | 壁・天井:準不燃以上 |
| 特殊建築物 └・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 ・病院、患者の収納施設がある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、こども園など) ・百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店・物品販売業を営む店舗) | 壁:難燃以上 (床面上1.2m以下除く) 天井:難燃以上 (3階以上の居室は準不燃以上) | 壁・天井:準不燃以上 |
| 窓などの開口部がない居室 | 壁・天井:準不燃以上 | 壁・天井:準不燃以上 |
| 3階建て以上で延べ面積が500㎡超の建物 2階建てで延べ面積が1,000㎡超の建物 平屋建てで延べ面積が3,000㎡超の建物 | 壁:難燃以上 (床面上1.2m以下除く) 天井:難燃以上 | 壁・天井:準不燃以上 |
| 調理室、浴室などで、かまど、こんろ、その他火器が設置してある居室 | 壁・天井とも準不燃以上 |
建築基準法における内装制限の具体的なルールとは?
内装制限の理解には、具体的にどのような基準が存在し、どのような材料が使用可能なのかを知ることが必要です。
ここでは、内装材の分類や使える部位、また制限の例外についても詳しく解説します。
不燃・準不燃・難燃の違いと使用箇所の基準
建築基準法では、建物の内装に使う材料の燃えにくさに応じて、「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3区分を設けています(建築基準法施行令第108条の2、および国土交通省告示)。
不燃材料は、加熱しても燃焼せず、発煙や有毒ガスの発生がほぼない材料で、もっとも高い耐火性能を持ちます。石膏ボード(厚さ12mm以上)、スレート、コンクリートなどが代表例です。
準不燃材料は、20分間の加熱で燃焼しない材料で、内装の壁や柱の化粧材などによく使われます。
難燃材料は、10分間の加熱で燃えにくいとされる材料ですが、他と比べて火に弱く、使用箇所が限定されているのが特徴です。
内装計画の初期段階からこれらの区分を理解し、対応することが重要です。
天井・壁・カウンターなど、制限がかかる内装部位
内装制限がかかる代表的な部位は「天井」と「壁」であり、火災時に煙や炎が一気に広がりやすい面積の広い箇所です。
これらの部位には、不燃材や準不燃材など、建築基準法に適合する内装材の使用が義務づけられています。
また、客席のあるホールや飲食店舗などでは、カウンターや間仕切り、さらには大型の装飾物も制限対象になることがあります。
国土交通省の告示では、こうした部位ごとの具体的な仕様が示されており、誤って一般的な木材などを使用すると違反となるため、注意が必要です。
例外規定や緩和措置があるケース
すべての内装部位に一律で制限が課されるわけではなく、建築基準法には例外規定や緩和措置も存在します。
たとえば、天井高が3メートル未満で客席が設けられていない場合や、建物の使用頻度が極めて限定的な場合には、準不燃材の使用が認められるケースもあります。
また、一定の面積以内であれば、装飾用の材料として燃える素材を使える「面積緩和」が適用されることも考えられるでしょう。
これらの規定は建築基準法施行令第128条の3の但し書きなどで明記されており、設計時に十分な検討が必要です。
緩和措置を適用する場合も、設計者や自治体への事前確認は必須です。
建築基準法における内装制限違反がもたらすリスク
建築基準法における内装制限違反がもたらすリスクは、主に以下の通りです。
- 確認申請が通らない・完了検査に通らない
- 違法改装とみなされる
- 火災時の責任・保険金不支給の可能性
詳しく解説します。
確認申請が通らない・完了検査に通らない
建物の新築や大規模改修を行う場合、建築基準法第6条に基づいて建築確認申請を提出し、適法性の審査を受ける必要があります。
内装制限に適合しない材料を使って設計していると、そもそも確認申請の段階で不適合と判断され、工事着手ができなくなります。
また、工事完了後には完了検査(法第7条の2)を受ける義務があり、内装制限を守っていなければ検査済証の交付がされません。
検査済証がなければ、不動産としての価値が下がったり、金融機関の融資やテナント契約にも支障が出る可能性があるのです。
違法改装とみなされる
内装制限に違反した状態で工事を行った場合、建築基準法第9条に基づいて「違反建築物」として行政指導・是正命令を受ける対象になります。
特に用途変更や内装リフォームを行った際に、仕様変更を届け出ずに規制を無視したまま営業を続けると、監督官庁による立入検査で発覚するリスクがあり、営業停止や改修命令、最悪の場合は使用停止命令が下されることもあります。
行政の是正命令に従わない場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があり(同法第101条)、経済的・社会的ダメージが大きくなるでしょう。
火災時の責任・保険金不支給の可能性
建築基準法に違反して燃えやすい内装材を使用していた場合、万一の火災発生時に被害が拡大し、人的・物的損害の責任を問われる可能性があります。
特に第三者に死傷者が出た場合、民事上の損害賠償責任だけでなく、刑事責任が問われるリスクも否定できません。
また、火災保険や店舗総合保険に加入していても、契約内容に「法令違反に起因する損害は免責」といった条項が含まれていることが多く(保険法 第17条の趣旨に準ずる)、違法内装が原因と認定されれば保険金が支払われない可能性もあります。
こうした経済的リスクも十分に考慮する必要があるのです。
トラブルを防ぐために今すぐできる対策
内装制限によるトラブルを未然に防ぐには、主に以下の対策を行う必要があります。
- 設計前に管轄自治体へ確認しておく
- 施工会社・内装業者と法令対応の確認を徹底
詳しく解説します。
設計前に管轄自治体へ確認しておく
内装制限の適用範囲や必要な耐火性能は、建物の用途・規模・構造などによって異なるため、設計の初期段階で必ず所轄の建築指導課などに確認を取るべきです。
多くの自治体では、事前相談の窓口を設けており、図面や用途計画を提示すれば、必要な内装材の区分(不燃・準不燃・難燃など)を確認できます。
自治体の公式サイトには、「建築計画概要書」や「防火対象物の確認チェックリスト」などが公開されている場合もあり、これらの資料を活用すると精度の高い設計につながります。
建築確認申請の前にこうした手続きを踏むことで、重大な設計ミスややり直しを防げるでしょう。
施工会社・内装業者と法令対応の確認を徹底
設計者だけでなく、実際に施工を担う工務店や内装業者にも、建築基準法への理解と対応が求められます。
特に商業施設や飲食店などの内装工事では、見た目の美しさやコスト重視で、誤って不適合の内装材を選定してしまうリスクがあります。
施工業者に対しては、仕様書や設計図に内装制限への対応内容を明記するだけでなく、使われる材料が国交省の「不燃認定番号」を持っているか、事前に確認しましょう。
また、工事中に設計変更があった場合も、その都度、再確認する体制を整えることが重要です。
信頼できる業者と密に連携し、定期的な打ち合わせを行うことが、違反リスクの最小化に直結します。
まとめ:内装制限はプロと連携して正しく対処を

建築基準法における内装制限は、単なるデザイン上の制約ではなく、法的義務であり、命を守るための重要な安全対策です。
違反すれば、建築確認が下りないだけでなく、火災時の責任や保険金の不支給など、取り返しのつかないリスクを伴います。
そのため、建築士や施工業者だけでなく、発注者や店舗経営者も最低限の知識を持ち、早い段階で自治体と連携しながら対応することが欠かせません。
わからないことがあれば、ためらわず専門家に相談し、トラブルを未然に防ぐ意識を持ちましょう。
八幡建装は、千葉県市川市や船橋市、東京都23区を中心に店舗内装工事を行っており、特に美容室の施工実績が豊富です。
無料で物件選びに同行してもらえるため、お客様の理想に近い物件を選びやすく、完全自社施工管理により中間マージンも一切ありません。ぜひ一度相談してみてください。
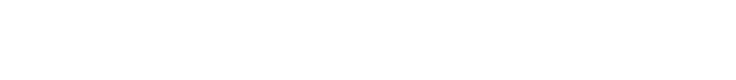
-1.jpg)