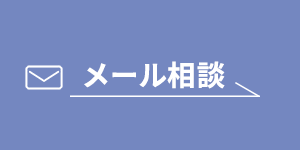店舗内装の耐用年数と減価償却の関係性とは?勘定科目や注意点なども解説
著者:八幡建装 株式会社
店舗の内装工事を検討する際、どの費用を経費として計上できるのか、また耐用年数によって減価償却の扱いがどう変わるのかを正しく理解することは、賢い資金計画のために欠かせません。
特に建物本体・付属設備・備品などの分類によって会計処理が異なるため、適切な知識が必要です。
本記事では、店舗内装の耐用年数と減価償却の関係性を踏まえ、勘定科目や注意点なども解説します。
八幡建装は、千葉県、東京都全域で店舗工事を行っており、美容室や飲食店などの施工実績が多数ございます。
見積もりの段階で自社でできること、できないことを明確にし、最適なプランをご提供します。ぜひ一度相談してみてください。
目次
店舗内装の耐用年数とは

店舗内装の耐用年数とは、税法上の資産として定められた使用可能な期間を指します。これは法人税法や所得税法に基づき、内装工事費用を減価償却する際の基準です。
耐用年数は内装の種類や材質、設備の内容によって異なり、例えば、木造や鉄骨造など建物の構造によっても異なる規定が設けられています。
適切な耐用年数を理解し、それに基づいた減価償却を行うことで、税務上の適正な処理が可能となり、経営上のコスト管理にも役立ちます。
店舗内装に伴い耐用年数と減価償却の関係性
店舗内装の耐用年数は、減価償却と密接に関係しています。
減価償却とは、内装工事などの設備投資を一度に費用計上するのではなく、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ費用として計上する会計処理です。
これにより、資産価値の減少を適切に反映し、事業の収益に対する正確なコスト配分が可能となります。
例えば、店舗の内装工事が耐用年数15年と定められた場合、工事費用を15年にわたって分割し、毎年決まった金額を経費として計上します。
適切な耐用年数を適用しないと、税務上の問題が生じる可能性があるため、正確な計算が求めらるでしょう。
店舗内装の耐用年数と勘定科目

内装工事費を支払った際、耐用年数の勘定科目として挙げられるのが、主に以下の通りです。
- 店舗本体
- 建物付属設備
- 備品
- 諸経費
詳しく解説します。
店舗本体
店舗本体の耐用年数は、建物の構造によって異なります。
鉄筋コンクリート造の店舗は47年、鉄骨造の場合は19年または34年、木造建物は22年と規定されています。
店舗本体は、建物そのものの資産価値を維持するため、耐用年数が長く設定されているのが特徴です。
建物本体の改装を行う際には、資本的支出として処理し、減価償却を行うことが求められます。
一方で、単なる修繕やメンテナンスであれば、修繕費として一括費用計上が可能な場合もあります。
建物付属設備
建物付属設備とは、照明や空調、給排水設備など、建物に固定されている設備です。法定耐用年数は建物本体とは異なり、一般的に15年と設定されています。
例えば、エアコンや電気設備などの設備投資を行った場合、それぞれの耐用年数に基づいて減価償却を行う必要があります。
建物付属設備の耐用年数を誤って建物本体と同じ扱いにすると、税務上の指摘を受ける可能性があるため、正確な仕分けが求められるでしょう。
備品
店舗内で使用する什器や家具、厨房機器などは「備品」として扱われ、耐用年数がそれぞれ異なります。
具体的には、事務机や椅子は8年、冷蔵庫や厨房機器は6年、パソコンは4年と定められています。
これらの耐用年数を適用することで、計上する減価償却費が適正になり、税務処理の際に問題を回避できるでしょう。
なお、少額の備品(10万円未満のもの)は、一括費用計上が可能な場合もあります。
諸経費
内装工事に伴う諸経費として、設計費や仮設工事費などが発生します。
これらの経費は、内装工事全体の一部として資本的支出に含める場合と、一定条件のもとで修繕費として処理できる場合があるでしょう。
例えば、店舗のレイアウト変更のための設計費は資本的支出に該当し、減価償却の対象となります。
一方、壁紙の張り替えや配線の一部変更などは修繕費として一括計上が認められるケースもあります。
店舗内装工事を減価償却する際の注意点
店舗内装工事を減価償却する際、主に以下のことに注意する必要があります。
- 自己所有建物と賃貸物件で耐用年数が異なる
- 建物附属設備の法定耐用年数は建物と比べて耐用年数が短い
- 設計費や仮設工事費は経費にできない
詳しく解説します。
自己所有建物と賃貸物件で耐用年数が異なる
店舗を自己所有している場合と、賃貸物件を借りている場合では、適用される耐用年数が異なります。
自己所有の建物であれば、建物本体や付属設備ごとに定められた法定耐用年数を適用します。
しかし、賃貸物件の場合は、契約期間に応じて耐用年数を短縮することが可能です。
例えば、契約期間が10年の賃貸物件に内装工事を施した場合、法定耐用年数ではなく、契約期間に基づいた短縮耐用年数を適用できます。
建物附属設備の法定耐用年数は建物と比べて耐用年数が短い
建物附属設備の耐用年数は、建物本体の耐用年数と異なり、一般的に15年と短めに設定されています。
例えば、エアコンや給排水設備は、建物の構造に関係なく耐用年数が短いため、建物本体と分けて減価償却を行う必要があります。
この区別を怠ると、税務上の指摘を受ける可能性があるため、設備ごとの正しい分類が重要です。
設計費や仮設工事費は経費にできない
店舗内装工事の際に発生する設計費や仮設工事費は、修繕費として処理することができず、資本的支出として減価償却の対象です。
例えば、新規の内装デザインを依頼した際の設計費や、一時的な足場設置費用などは、原則として耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。
そのため、これらの費用を一括で経費計上することはできず、長期的な費用配分を前提とした資産計上が求められます。
店舗内装の耐用年数はしっかりと理解しておこう

店舗の内装工事を行う際には、耐用年数の考え方をしっかり理解し、適切な減価償却処理を行うことが重要です。
耐用年数を正しく適用することで、税務上のリスクを回避し、資産管理を適正に行うことができます。
また、賃貸物件と自己所有物件では異なる耐用年数が適用されるため、事前に確認しておくことが必要です。
八幡建装は、千葉県、東京都全域で店舗工事を行っており、美容室や飲食店などの施工実績が多数ございます。
見積もりの段階で自社でできること、できないことを明確にし、最適なプランをご提供します。ぜひ一度相談してみてください。
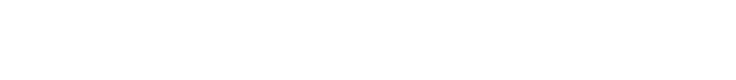
-1.jpg)